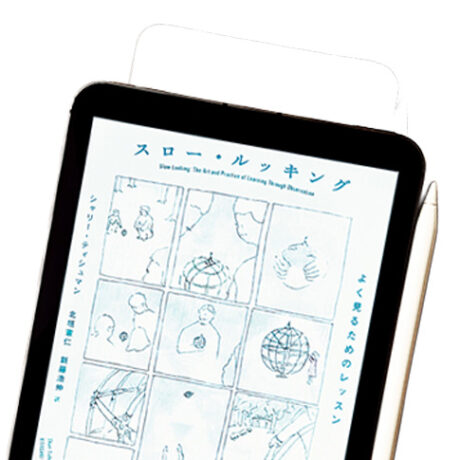時代はタイパ・コスパより「スロー・ルッキング」⁉︎⁉︎
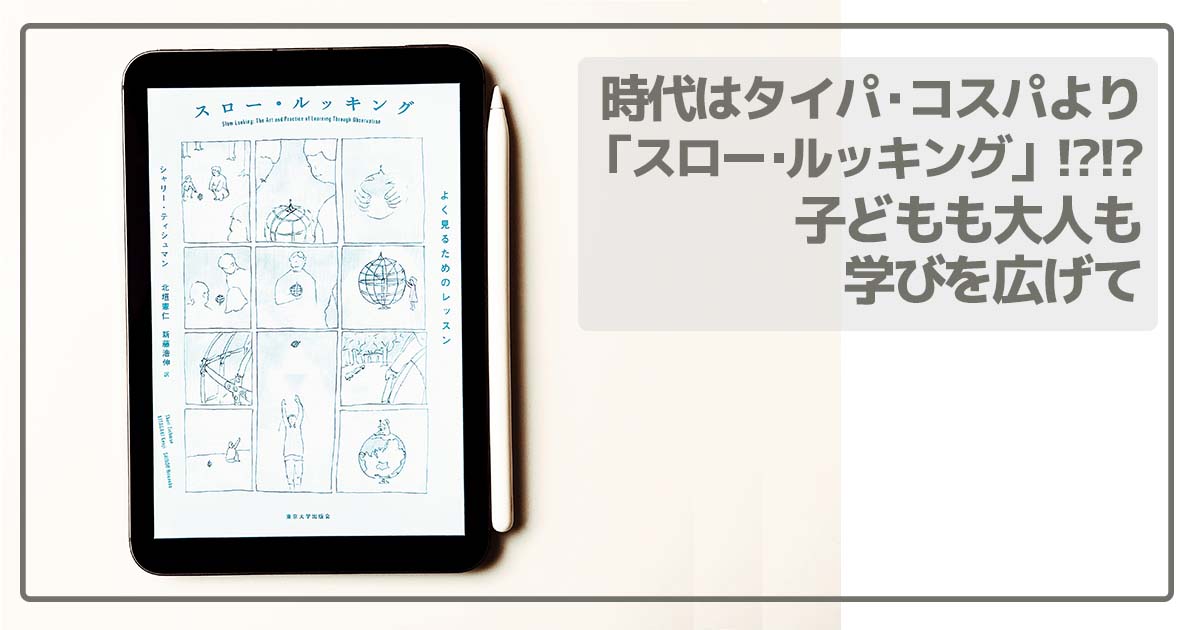 時代はタイパ・コスパより「スロー・ルッキング」⁉︎⁉︎
時代はタイパ・コスパより「スロー・ルッキング」⁉︎⁉︎
時間をかけて「見る」ことで変えられることとは?
シャリー・ティッシュマンさんの『スロー・ルッキング』(東京大学出版会、2025年)を読んだ。「スロー・ルッキング」で、子どもも大人も「学び」を広げてしあわせに!
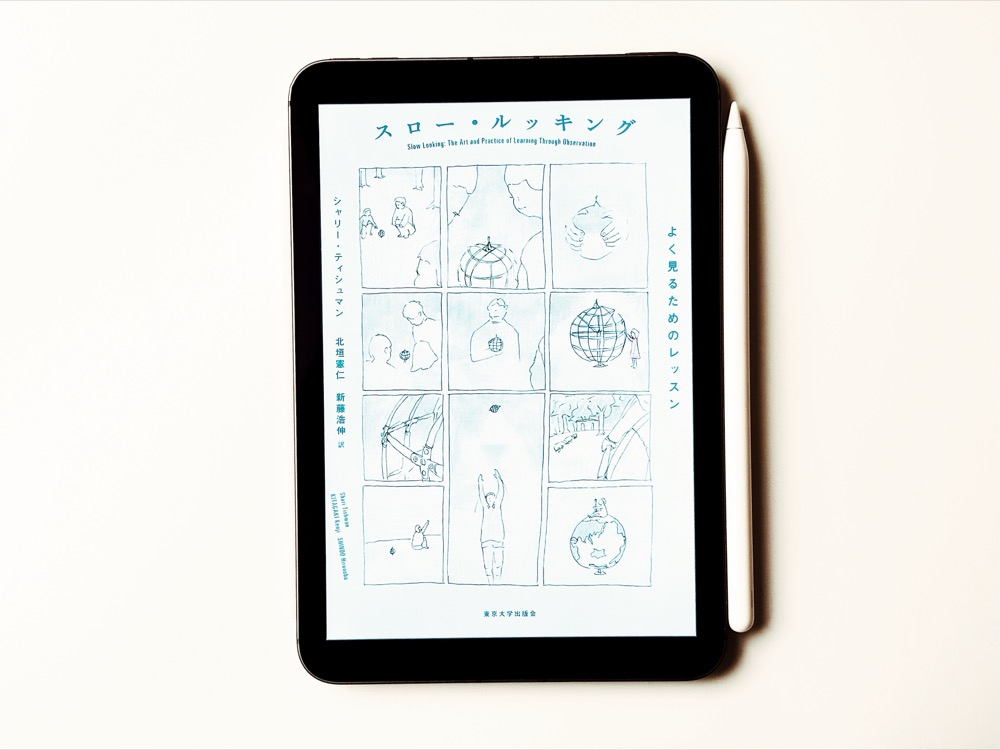
『スロー・ルッキング』(東京大学出版会、2025年)
見るということ
「見る」という活動を、わたしたちは絶え間なくしている。ただ、「わたしは今、見ている」と、明確に意識する瞬間やひとときというのは限られている。ときおり、「見る」ことが意識の中心に来る瞬間やひとときがあるわけだが、それは、どんなときで、どんな風に見ているだろうか?
日常的にしがちなのは、サッと見て意味を把握するといった活動だ。視線を走らせるときでも意味を追いかける。物語や説明を求めるのだ。けれども「見る」ことには、もっと違うやり方もある。
「実況中継」で見るー『センスの哲学』から
千葉雅也さんの『センスの哲学』(文藝春秋社、2024年)では、多くの人がもっとセンスがよくなりたいと考えているけど、誰もが努力で、よくしていけるような種類の「センス」があるよ、それは、デートでの出来事でも、映画でもいい、意味から離れて「並び」に集中してみるという方向性をもつことで、よくしていけるよ、と読者に語りかけていた。
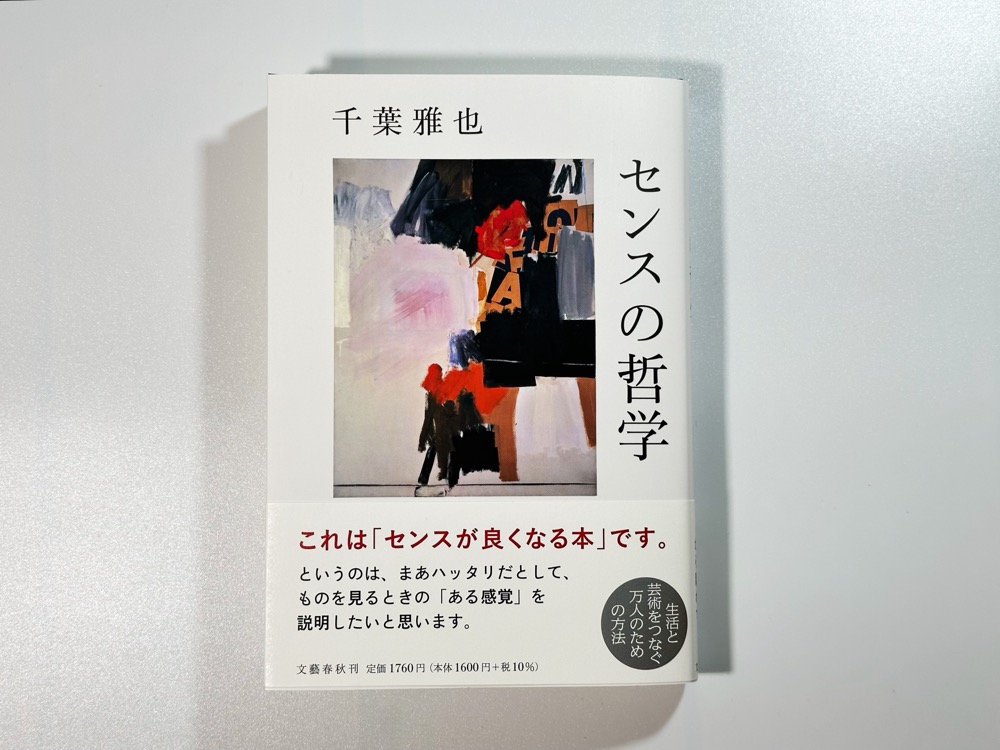
千葉雅也さんの『センスの哲学』(文藝春秋社、2024年)
机の上のスタンドライトを見るときに、「下にボンッと丸い台があって、上に視線を動かすと、キュッとすぼまって細い柱になり、それがヒューッと上に伸びている。すると傘の部分があって、またボンッと開く。」というように、物を見るとき、時間的に展開してみること、あるいは、現代絵画の画面を時間的に展開して、言葉で記述してみることなど、してごらんとも紹介されていた。一目で全体をパッと把握して見るのではなく、いわば、「実況中継」して見るわけだ。(「実況中継」という言い表し方は、大学の授業で、この本の内容をとりあげたときに、学生のKさんがおっしゃってくださったものだ。)
「見る」ことのモードを意識的に変えるための手立ての一つ スロー・ルッキング
スロー・ルッキングも、「見る」ことのモードを意識的に変えるときの一つの手立てを提供するものだといえるだろう。そして、それは、「学び」の可能性を広げるものだとティッシュマンさんはいう。
「学び」で重視される高度な活動としては「考える」がある。そして、学び手がどのように思考するか、に注目が集まりがちだ。しかし、「学び」において、ゆっくり時間をかけて見るということ、スロー・ルッキングも、とても重要だというのだ。
「学び」に価値ある「スロー・ルッキング」
認知心理学者も「ファスト・マインド(fast mind)」と「スロー・マインド(slow mind)」について語ってきており、思考に関しては、熟慮する心を鍛えることの価値に異を唱える人はほとんどいない。一方で、ゆっくり見ること「スロー・ルッキング」が「学び」に価値あるということには、なかなか思い至らない傾向が世間や学校にはある。
芸術作品を見るときにも、自然を見るときにも、あえて時間をかけて見ることで「学び」を深めていくことができる。本書は、そのコツを整理して考える助けも数々、具体的に紹介してくれている。
スロー・ルッキングは「足場かけ」に向いている
「足場かけ(scaffolding)」という教育研究の世界で使われてきている言葉がある。教育者が何をすべきかを教えて、段階的に指示するのではなく、学び手が自分で何かをできるようなサポートととなる足場を提供する、という教育方法の考え方だ。スロー・ルッキングは足場かけに向いているという。
博物館や美術館では、来館者がパッと見ただけの状態からスロー・ルッキングへと移行することを実際に促しているといっていい実践が、これまでにもあった。持続的な観察に取り組むためには、大人よりも子ども・若者の方が、サポートを必要とするといった誤解が広くあるため、そうした実践は、子ども・若者向けの事業でよく見られる。
構成主義の教育思想が根底にある
博物館で行われる、スロー・ルッキング的な、目で探究するプログラムは、学校教育における探究型学習の亜種と考えることができるかもしれない。探究型学習は、もともとは科学教育の文脈で開発されたもので、根底にあるのは、構成主義の教育思想である。構成主義とは、人は興味にもとづいた経験と反省の往還を通して世界に対する自分の理解を構成していくことで、もっともよく学ぶという考え方だ。
こうした考え方と相性のいい、思想家たちがいる。学校教育は、子どもが生まれながらにして持っている、自分で物事を見ようとする興味を引き出し、それを伸ばすために組織されるべきだと考えていた思想家、コメニウス、ルソー、ペスタロッチ、フレーベル、アガシー、デューイらだ。彼らについても、ティッシュマンさんは紹介してくれていて、学びに関する思想への誘いもしてくれている。
ものづくり教育や医学教育にもスロー・ルッキング
見ることというと、静的な感じがするが、スロー・ルッキングは、「ものづくり教育者」を自認する教育者にも人気だという。複雑なものを必ずしも分解することなく、見分け、理解することができるからだ。身の回りにあるものやシステムの部分や目的を理解することで、それらのものやシステムを再認識し、再設計し、再発明することができるようになるのだ。
また、スロー・ルッキングは、単なる視覚分析技術の向上に貢献するだけのものではないことが、美術館と医科大学の連携プログラム「見ることを学ぶ(Learning to Look)」というプログラムでもわかっているそうだ。共感的なコミュニケーション、思いやり、文化的な違いへの気づき、文化的な偏見、創造性などに関係するスキル向上が見られるプログラムは、医学生たちの臨床実践の向上にも有益だと考えられているという。
さらに、スロー・ルッキングで、幸福感が増すというのが、おもしろいポイントだろう。どういうことだろうか?本の中に出てくる。
コロンブスの卵か?スロー・ルッキング
スロー・ルッキングで「学び」の可能性を広げるという考えは、コロンブスの卵かもしれない。今まで、ことさら、取り上げてこられたことがないけれど、多くの人は、言われてみれば、当たり前のことのようにも感じるのではないだろうか。しかし、当たり前にも感じられることが、しっかりと、その性質や価値について考えられてきていなかったり、軽んじられてきた実態に注目したことは高く評価されるべきだろう。
スロー・ルッキングについて、実際に実施された学校や博物館・美術館等でのプロジェクトや調査などの実践と、科学史的な観察概念の歴史・教育思想などなどの理論を駆使して、具体的な手立てもまじえつつ詳細に描き出した本書は、仕事や家庭で教育に携わっている方はもちろん、何かの「学び」に取り組んでいる方にとっても、「見る」ことについて考えている方にとっても、大いなるヒントを得られるかもしれない一冊となっている。
あなたも続きが書きたくなる
特に学校教育、博物館・美術館教育に関わっている方にとっては、まだまだ、続きが自分にも書けそう!とキョーレツに思わせてくれる必読の一冊だ、と電子書籍を読み終えて書いてから、出版社のサイトの書影で本の帯を見たら、「学校および博物館・美術館関係者必読」と書かれてた(ギャフン)!
この本、あなたも続きが書きたくなるにちがいない。あなたなら、どんな続きを書かれるだろうか?
![兵庫教育大学大学院 芸術表現系教育コース[美術分野] 兵庫教育大学大学院 芸術表現系教育コース[美術分野]](https://finearts.hyogo-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2021/12/wp-logo-art-1.png?1770172155)